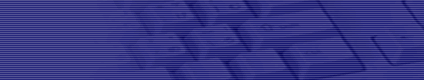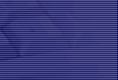基本情報技術者試験のネットワーク基礎:DNS(Domain Name System)とは?
DNS(Domain Name System)は、インターネット上で使われる「ドメイン名」をIPアドレスに変換する仕組みです。
ユーザーが使いやすい文字列のURL(例:www.example.com)を、機械が通信できる数値(例:93.184.216.34)に変換します。
DNSの基本的な役割
- ドメイン名とIPアドレスを対応付ける(名前解決)
- ユーザーはIPアドレスを意識せずにWebサイトにアクセス可能
- 世界中で分散管理されている
名前解決の例
www.example.com → DNSを通じて → 93.184.216.34
DNSの仕組み(名前解決の流れ)
- ユーザーがブラウザでURLを入力
- PCやスマホがDNSサーバに名前解決を要求
- DNSサーバがIPアドレスを返す
- そのIPアドレスに向けて通信が行われる
DNSの構成要素
- ドメイン名: インターネット上の名前(例:example.com)
- DNSサーバ: ドメイン名とIPアドレスの対応表を管理するサーバ
- ルートDNS・TLD DNS・権威DNS: 名前解決を階層的に処理するサーバ群
DNSの階層構造
- ルートドメイン: (.) ← 最上位
- TLD(トップレベルドメイン): .com、.jp、.net など
- セカンドレベルドメイン: example(example.comの"example")
- サブドメイン: www(www.example.comの"www")
キャッシュの利用
- DNSの応答結果は、キャッシュとして一定時間保存される
- 頻繁な名前解決の負荷を軽減する仕組み
基本情報技術者試験での出題ポイント
- DNSの役割(ドメイン名とIPアドレスの変換)
- 名前解決の流れとDNSサーバの種類
- 階層構造の理解(TLDやサブドメインの意味)
学習のコツ
- 実際にURLを入力してアクセスする流れを意識する
- 「DNSとは住所録のようなもの」と例えると覚えやすい
- ドメインの階層構造を図で整理すると理解しやすい
まとめ
- DNS: ドメイン名 ⇔ IPアドレスの変換を行う仕組み
- インターネット通信に不可欠な基盤技術
- 試験では仕組み・流れ・役割の理解が問われる
DNSは、ユーザーが意識せずとも日常的に使っている重要な技術です。
試験では図解問題や語句選択問題として出題されやすいため、階層構造と名前解決の流れを押さえておきましょう。