

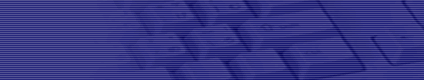
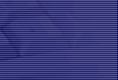
|
関連用語集 |
応用情報技術者試験のモデリング技術:ユースケース図とは?ユースケース図とは、システムの利用者(アクター)と、そのシステムに期待される機能(ユースケース)の関係を視覚的に表す図です。 ユースケース図の目的
ユースケース図の構成要素
例:図書館システムのユースケース図
【アクター】 【ユースケース】
利用者 ─────────→ 本を検索する
─────────→ 本を予約する
─────────→ 本を借りる
管理者 ─────────→ 本の登録・削除
関係の表現
ユースケース図の特徴
応用情報技術者試験での出題ポイント
学習のコツ
まとめ
ユースケース図は、ユーザーのニーズを機能へと落とし込む「橋渡し」の役割を果たします。 |
|
就転職をお考えの方へ |
|
就転職活動は一人で悩みを抱えてしまうものです。 でも当学院の就転職サポートなら、 カウンセリングから企業紹介・履歴書・面接対策、就職後のキャリア相談まで "長期的に寄り添う"就転職サポート体制を確立しています! 安心の就転職サポートと万全の学習サポートで社会で活躍する修了生も多数。 是非、ご閲覧下さい!
|
